第3回全国町並みゼミ函館集会特集号
S55.9.1発行
発行所 函館の歴史的風土を守る会
印刷所 三和印刷
さる5月27日、20年周期でしか訪れないと言われている、全国町並みゼミが、ここ函館で開かれた。港を一望する丘に建つ歴史的建造物、市公会堂を会場として、北は小樽から南の長崎まで全国を網羅する各地から80余名地もと参加約200名による集会であった。望ましい歴史的環境の保存、再生をテーマに、市民、行政、学識専門家、夫々の立場での地区報告がなされた。歴史的環境、町並み保存を都市計画の中で模索していかなければならない函館にとっても、またとない価値ある集会であったと思う。
主催は全国町並み保存連盟である。以下、当日の状況を限られた紙面の中で再現し皆さんにお伝えします。
本日は全国各地からおいでの皆様方、ようこそおいでくださいました。今朝は早くから市内見学いかがでございましたか。只今から全国町並み保存連盟主催の第3回全国町並みゼミ函館集会を小樽に引き続き開催いたします。
最初に開会のご挨拶を連盟副会長の山田さんにお願い致します。山田さんは川越市文化財保護協会会長です
開会挨拶
全国町並み保存連盟副会長 山田 勝利
只今ご紹介にあずかりました全国町並み保存連盟の山田でございます。第3回全国町並みゼミを小樽、函館において開催することができましたのは、地元各位の絶大なるご協力の結果によるものと深く感謝申し上げます。
ご承知のごとく高度成長下にあって豊かな生活環境、美しい町並みは破壊され全国至る所個性を失った画一化が進んでおります。本日函館市内をご案内いただきましたが、さすがに歴史の町、海と山との自然に恵まれた町としての函館の美しさに深く感動した一人でございます。
しかし、都市は生き物だと言われています。この美しい皆様の町も、今後どの様に変化するでありましょう。
また本日拝見いたしました、特に函館の歴史の証人であります企業体建造物群の保存と再生につきましては、いろいろの問題が提起されることと存じます。本日のゼミが、住むに価し、文化の香り高い函館らしい町づくりを希望しておられます皆様方に、多少なりともお手伝いできますことを心から念願いたしまして、開会のご挨拶とさせていただきます。
全国町並み保存連盟に対しまして、市長さんから、花束の贈呈がございます
―市長(代理)から山田連盟副会長に花束―
司会 全国町並み保存連盟顧問朝日新聞 石川 忠臣
函館の歴史的風土を守る会 田中 雪子
挨拶と報告をかねまして、地元から函館の歴史的風土を守る会の会長 今田光夫が致します
挨拶と報告
函館の歴史的風土を守る会会長 今田 光夫
「函館の歴史的風土を守る会」が誕生しましたのは、この下にある北海道庁渡島支庁庁舎の古い建物を野幌に移転することに決議されました当時”歴史的建造物はその土地にあってこそ価値がある”ということから現地保存運動を展開したことにはじまります。
只今皆様をお迎えしていますこの公会堂は、明治43年の建造で、72年を経過しています。この場所は松前の藩政時代の奉行所の跡地で、その後2回にわたって幕府が直轄したいわば天領でその時期にも箱館奉行所が置かれていた場所であり、更に溯れば約500年前に河野氏が館を築いた跡地で北海道でも最も古い歴史を担っています。
函館の街は和洋の建築が混在しているところに一つの特徴があろうと思われます。つまり洋風のものを受け入れた初期の形が残っていることにお気づきと思います。こうしたことは全国的にも比較的例を見ないことです。
私どもは函館の歴史を尊重したいと思っています。歴史研究は実証の科学であります。ですからそこに残された歴史的遺構というものは、文献にもまして貴重なものその保存に今後も全力を尽くしたいと願っています。
現在私どもの会は、近代建築の一つ一つについて調査を進め、可能なものから逐次市の指定にとり運んでいく努力を続けています。しかしこれはあくまでも点の確保にすぎません。函館の文化を残していくためにはそれを面にまで拡大していかなければならない。そのためには条例などで手厚い保護を加える必要がある。それがどういう姿をとるべきかは、これからの課題でございます。
壇上を整理しまして司会を交替しました、町並み連盟の石川です。司会はアマチュアですのでご協力ください。今壇上に座っていただいた方は、町並みゼミのスターでありその他大勢でもあります。この方々によって、第3回全国町並みゼミでどんなことが行われたか、概略がわかる形でお話しいただきます。
全国町並み保存連盟とは
朝日新聞編集委員 木原 啓吉
最初に全国町並みゼミがどうして生まれ、どんな形でやって来たか朝日新聞編集委員の木原さんにお願いします。
この町並みゼミを主催している全国町並み保存連盟の性格をまず説明しておきたいと思います。
昭和49年に有松絞りで有名な名古屋の有松と、日本の町並み保存運動では先進的位置にある木曾の妻籠、それに中世から近世初期の民家集落では日本で最大規模といわれる奈良県の今井町、この3つの地区の住民が集まって町並み保存連盟というのを作りました。
それから年々メンバーが増えまして、一昨日までは18団体ありました。妻籠を愛する会・今井町を保存する会・有松まちづくりの会それに大阪の富田林寺内町を守る会・長野県の奈良井宿保存会・愛知県の足助の町並みを守る会・香川県のこんぴら門前町を守る会・近江八幡市のよみがえる近江八幡の会・愛媛県の内子町八日市周辺町並み保存会・埼玉県の川越市文化財保護協会・京都の祇園新橋を守る会・三重県の伊勢河崎の歴史と文化を育てる会・長野県の大平宿をのこす会・滋賀県の城下町彦根を考える会・会津喜多方の会津北方風土会・同じく会津若松市の会津復古会・小梅運河を守る会・小樽夢の街づくり実行委員会、このように日本列島の各地で歴史的環境を守っている住民の団体です。一昨日の総会で函館の歴史的風土を守る会と長崎の中島川を守る会が新たに加わって現在20団体、これで九州から北海道まで各ブロック全部の連絡組織ができあがったわけです。
この会の姉妹団体として全国歴史的風土保存連盟というのがあります。これは昭和39年頃、高度成長期の中で各地で歴史的風土が破壊された。最も顕著だった鎌倉の鶴岡八幡宮の裏山に住宅団地を造る問題が起きたのをきっかけに、古都京都、奈良、鎌倉などの歴史的風土を守る保存連盟ができまして、車の両輪のように今日まで歴史的環境の保存をやってまいりました。
全国町並みゼミは、全く手弁当で集まる住民の会で、第1回は53年4月22、23の2日間、名古屋の有松と足助町を舞台に開かれました。この時は全国から140人、地元参加を含めて400人ほどの集会でした。第2回は昨年で滋賀県近江入幡市で市の青年会議所などの協力で、全国から200人地元参加を含めて400人ぐらいで行われました。そして今回第3回は、御地と小樽で開かれたわけです。
ではどのような会かというと、手弁当で集まることと同時に、門戸開放というか、歴史的環境を守るというただその一つの目標のために、いろいろな職業いろいろな立場の方が、進んでしかも平等の資格で参加するということが、一つの特徴になっています。ですから各地の住民運動の方、学者研究者の方が多数参加しておられます。こうした運動では珍しいのですが、行政関係、地方自治体で歴史的環境問題を担当しておられる役人の方、中央官庁の国土庁、建設庁、文化庁などの職貝の方たちが来られ、今回も国土庁から3人のほか、建設庁、文化庁からも見えております。
小樽で開かれた第3回全国町並ゼミでは、まず記念講演として東京大学の大谷幸夫教授が「町並み保存と現代都市計画の課題」というテーマでお話なさいました。歴史的環境の問題は都市計画とますます密接な関係をもってきており、その問題点を指摘されました。
それから特別報告として小樽運河を守る会の代表が「水と緑と歴史の町づくり」というタイトルで、小樽運河をめぐる問題点と今後の都市再生と創造の問題を話されました。
その後函館をはじめ各地からの報告ということで31の団体住民運動のほかに、環境文化研究所・日本ナショナルトラストなどからの報告がございました。
今回の町並ゼミの一つの特徴は、このほかに3つの分科会を設けたことです。この分科会の内容と、最後に行われた小樽函館宣言については、後ほど報告があります。
こうした住民の団体は、日本では環境破壊が始まった60年代後半から、自然保護の団体、入浜権の自然海岸を守る運動、歴史的環境というふうにテーマごとに各地で集会をしており、これは60年代からの日本の歴史の上でも画期的な住民運動ではないかと思われます。世界的に見てもこうした計画のものにイギリスのナショナルトラスト、歴史的環境を守るシビックトラストなどの運動がありまして、事実非常な成果をあげており、法律ではシビックアメニティーズ法など都市の中の歴史地区の保存のための法律や、都市農村計画法などもできています。
この町並保存連盟や歴史的風土保存連盟なども、今後ますます大きな圧力団体に成長して、日本の文化行政、都市計画行政に役割を果たしていくものと思われます。既に文化財保護法の改正で町並み保存が実施され、これには事実連盟が大きな役割を果たしました。
次に今度の特徴であった分科会について、ここでどういうことが語られたかお話しいただきましょう。杉本さんは広島大学の若手でビカビカの助教授です。
分科会で話されたこと
広島大学工学部助教授 杉本 俊多
町並ゼミの全体集会では、各地からの報告が行われるわけですから、実際には一団体5乃至10分といった短い時間であり、内容的な追究はむずかしいということから今回から交歓討論ということで分科会を設けて、それぞれのテーマで内容をつきつめるということをしました。
今回は3つの分科会でしたが、検討した具体的テーマというのは次のようなものです。
第1分科会 保存運動と住民の理解
第2分科会 保存と開発の見直し
第3分科会 保存の制度 事業のあり方
しかもこの分科会全体に大きく掲げた問題は、保存の課題をのり越えて、ということで、今後さらに運動をおし進めていくためには、どういう課題をかかげてゆくかという観点から話し合ったわけです。
<第1分科会>
長崎の中島川の保存運動の展開について具体的な報告をいただき、そのあと保存運動と住民の理解というテーマにそって、報告を参考にしながら討論されました。その要点を申しますと、
○1祭のあり方を検討し、新しい祭を創造することによって、保存運動に住民一般のもり上がりを期待できるのではないか
○2住民運動に関連して、政党が関与してくるという形がとられることがあるが、住民運動の独自性主体性を考えれば、政党から独立して展開すべきだ
○3保存の対象を具体的にしぼって運動を拡大するばかりでなく、地域経済などとの関連を考えることによって、さらに内容豊かな運動を展開できるのではないか
○4保存運動が広がりを作ることを目標にするならば、運動に専門家、行政関係、学者研究者、特に教育者などより多くの参加者を、かつ多方面の人や他の環境運動などとの連帯を計らなければならない
保存運動は基本的には住民から生まれてくる運動であるから、運動にたずさわっている以外の住民との連帯でも同じ住民の一人という立場で地道な協力関係を求めていくべきだ
住民運動というのは将来的に町づくり運動全般の中核として機能するであろうし、そうした方向にもっていくことによって実り多いものにできるだろう
<第2分科会>
保存と開発の見直しというテーマで、伊勢の河崎から建設省から出された道路工事河川改修計画に対して、水害の根本対策にはふれられずに伝統ある町並みを崩壊させるものだとして反対運動が起こり、住民の方から現状から将来にかけてどういった方向に進むべきかという町づくリも含めた代案が提出され、住民主体の町づくり運動が既に展開されているという報告があった。
われわれが考えなければならないのは、住民主体の運動が行われている現状があり、これこそが、今後の計画を進めていく上で重要になってくるということである。
<第3分科会>
保存の制度と事業のあり方ということについて愛知県足助町からの報告があったが、制度上の間題には前面に大きな障害が立ちはだかっていることは一致して認めるところであり、具体的にどういった制度を追求し改革すべきかが検討された。
制度上の問題
○1保存の長期計画が必要である
○2自治体の中に専門関係に強い人ということで人材を養成する、または人材を専門家から派遣するシステムをつくる必要がある
○3都市計画決定の際に、文化的あるいは歴史的環境に対する視点を確保すべきである 都市計画決定には住民の協力を求める必要があり、現状での都市計画決定のあり方に対して批判していかなければならない
○4保存地区周辺に対する何らかの措置なり計画が必要である
財政上の問題
○1一般的に文化庁その他財政的補助金の絶対量が少ない都市計画サイドからの協力を要請すべきだ
○2税制面、特に固定資産税などにおいて配慮すべきだ
○3融資制度の検討ということで、保存公社あるいは住民財団・組合といった組織による融資制度の必要がある
以上各分科会の大体の内容を説明いたしましたが、今後専門家、学者、研究者への立場、あるいは課題といったものが町並みゼミの方から要求される形になるわけです。分科会という形式もさらに発展させる必要があるだろうというのが皆さんの意見の一致したところでした。
分科会についての報告を終ります。
(紙面の都合上要約整理しました)
―地区報告―あたらしい町自慢の創造
これから社会面に移っていこうと思います。家庭面が入ってくるかもわかりません。小樽でのテーマが”あたらしい町自慢の創造を”ということで、壇上の皆さんに、自分の町自慢をしていただきます。
地元の函館建築士会から、建築雑考の会を代表して鈴木さんに報告をいただきます。
函館
建築雑考の会Σ 鈴木 一博
建築雑考の会というのは、今から2年ほど前に、仕事の上の20代から40代の仲間が集まって、建築の技術的なことだけを追究するのではなく、その他諸々把握しておくべき重要なポイントがあるのではなかろうかということから、自然発生的に生まれて来た会と言えます。
会が設立された最初の1年は、技術的なものの追究にかなり心をとられましたが、2年めになってやっと、自然保護とか環境破壊の問題を考えていく上には、どうしても函館及び近郊の歴史を知らなければ無駄な面が出てくるのではなかろうかということで、文化財や函館の歴史、図書館史などを手がけるようになったのです。
そのさ中、札幌では会員300人ほどのハビタという会があることを知りました。初めて参加した小樽での全国町並みゼミでも、われわれとさして違わぬ年代の方々が、前向きの姿勢で活動を続けておられることに刺激をされまして、今後の動きに責任を感じている次第です。
建築雑考の会と申し上げたのは、建築に関係する人間が多く集まっているところからなのですが、建築というのは専門的知識を要求されると同時に、社会的責任も又大きいと思うわけです。例えば道立西高校の石垣の改修についても都市景観の上から問題があったわけです。全国一律の画一化が函館市内でも西部東部をとわず行われて来ています。この石垣も4、5年前であれば何のためらいもなく破壊され、一律的な工事が施されていたでしょう。西高校の場合は現在増改築にタッチしている設計事務所の方々が検討した結果現状を維持した形で残されることになったわけです。
保存すべきか取り壊すべきかの判断の基準をどのへんに見出すかということは、これからの大きな課題であろうと思うわけです。
このような姿勢で現在にいたっています。小樽での全国町並みゼミでは、皆さんが前向きに取組んでいられること。若い年令層の方も多いということなど、参考にもなったし刺激にもなりました。今後われわれも、謙虚に事に処していきたいと考えるわけです。
※この報告は開会の挨拶に続いて行われたものですが、紙面の都合でここに掲載しました。
開催地小樽の峰山さんは、小樽運河を守る会の二代目会長で主婦です。だれかがヒミコの名を献上しました。
小樽
小樽運河を守る会 峰山 富美
函館の方々に、心から私どもの運動をご理解いただいたお礼を申し上げます。
先ほど町を見てまいりました。緑が多いことと後から建てた建物が全体の調和の中に生きていて、町並みを保存する心がこの町には既にあるんだと感じました。
さて小樽の町自慢ということになるのですが、私たちの運河を守る運動と夢街の若者たちが中心になって、この第3回全国町並みゼミを小樽の町で開かせていただいたことが、私たちの運動に大きな力になりました。
私たちは行政の力も、経済界の人たちの協力も得られませんでした。やったのは本とうに運河を残そうという人たちでした。僅かの人間が寝る時間を割いてゼミの準備をしました。そしてまがりなりにも成功させることができました。あの若い人たちの力を、即私たちの運動の力に増し加えていくことができること、これが一つの自慢だと思います。
運河を守る運動といわれますが、実は小樽の町をどういう町にするかということが原点にあります。町づくりをする、運河を守る、ということはどういうことなのか学習しなければなりませんでした。その運河講座という学習会に集まった人たちの中でも、本とうに眼を輝かして学習してくれたのは若い人たちでした。小樽の町は、これからああいう若い人たちの町づくりに寄せる熱心さによって支えられていくのではなかろうかと思います。
運河は一度つぶしたら永久にもどりません。誇れるものがあるとすれば、私たちの運動をこんなに多くの人々が支えてくれたことです。住民の意識を掘り起こすためには外側からの力が必要です。全国的連帯の中で地方の文化が守られていくことを考えなければなりません。
今しなければならないのは、運河埋立ての問題を時間をかけて検討してもらうことです。また同時に若い人たちに町並みを残す心を育てていくことだと思います。最近小樽の小学生が”運河を絶対残してほしい。じゃ私にできることは何だろう”という作文を書いたことを知らされました。今すぐしなければならないこと。今後も続けて努力しなければならないこと。この両面から考えていかなければならないと思うわけです。
二つの海を越えて小樽と長崎が姉妹関係を結びました。片寄さんは長崎の大学の教授でグアラトシの主人公です。
長崎
中島川を守る会 片寄 俊秀
実は古いものを守るという話ですが、小樽のあの溝川の運河や倉庫群、ポッと見た時にはそれほど大したものだとは思わない。ところがじっと見ていると次第に心を豊かにしてくれるということがわかってくる。”いいんだ いいんだ”と気狂いのように言い出す人がいる。言われてみるとなるほどというのが、基本になっている。
函館でもそういう人が続々と現れたようで心強い。先ほどの建築士会の青年の話も非常にうれしかった。これから大いに地域に惚れ抜いてやっていただきたい。
私は建築学科の先生ですが、造るという方法だけでやって来たこれまでの建築技術のあり方には問題があったと思います。学生たちに本当の意味の建築を学んでほしいということで長崎の町について学び、その中で中島川を守り、町全体を守る運動にまで発展していきました。
長崎と函館は似ていると申します。美しさ歴史的環境も似ているが、問題点も似ている。造船不況をもろに被り、身障者やお年寄にはきつい坂と階段の町。こういう問題と保存の問題を同時に、または複合させて解決する。つまり現実の市民生活レベルから文化レベルまでを包み込んだ運動でなければ古いものは保存できないのです。
町並みといえば昔から京都。その京都の祗園新橋を守る会の会長の買手さん。京都の名人芸の職人さんです。
京都
祇園新橋を守る会 買手 正
私たちの住む京都祇園新橋は、皆さんご存知の花街です。日本の伝統芸能を観賞しながら心を憩わせる場を提供するお茶屋が並ぶ町です。このお茶屋町が高度成長の波におされて土地買収が進み、伝統を誇る祇園新橋がネオン街になろうとしたのです。
この町の主人公は女性です。その人達が”どんなこと言われてもかまへん”私たちがやるのは生きるための正義の運動。とわきまえて生活と営業を守るために、広く世間の皆様に訴えたわけです。
お茶屋を続けていくためには古い歴史、しかも美しい京の風情が漂う花街の環境、景観を大切にしなければならないわけで、これが祇園新橋の町並保存へと進んでいきました。町家は京都を代表する建築です。天井、梁、格子など日本建築における大工さんの技がこめられています。これは文化遺産であるという誇りをもっています。
わが町の自慢ということですが、長い争いの歴史の中で自衛することを身につけていった京都の人たちの真髄は町衆ということばにあります。運動の主役である女性たちの生き方の中に町衆の根性が連綿と生き続けていたことを自慢に申しあげて、お話を終らせていただきます。
町並と言えば忘れてならない木曽の妻籠があります。ゼロから出発して、70万人の観光客を集めるにいたった妻籠の町づくりについて。小林さんは役場の課長さんです。住民と課長さんの立場からどうぞ。
妻籠
妻籠を愛する会 小林 俊彦
木曽谷の小さな村、戸数300戸の妻籠宿は、昭和40年頃、高度成長の波をもろにかぶって若者が流失し過疎の村となっていました。文化イコール都市化と考えられていたその当時、とり残されたと思ういらだちのなかから村に残っていた若者たちが、何とかして村を守ろうと、数多くの試行錯誤を繰返すなかから考えていたのは、このままでは当然朽ち果ててしまう宿場のおもかげを残す町並みと、それに続く中山道や木曽桧の美林等の歴史的風土、それに島崎藤村の小説夜明け前の文学的ロマン等を加えてこれを保存し、かつ観光的に利用することでした。無価値のものを見方を変えることによって価値あらしめる、まさに発想の転換がおこなわれたのです。若者たちは幾多の苦闘を統けながら、住民総ぐるみの妻籠宿保存団体「妻籠を愛する会」を組織し、文化財と観光資源を「売らない・貸さない・こわさない」の三原則を立て、保存がすべてに優先するという大義の旗をかかげ、妻籠宿の保存をすすめてきました。遂には行政町・県・国をも動かすことに成功しました。妻籠は今や、その名を全国・世界に知られ、15年前気息奄々であったことを忘れたように、年間70万人の観光客が訪れ、名実共に潤っているのです。
一方行政は、住民が保存への胎動を始めると同時にこれに対応し、運動を文化財保護運動としてとらえ、住民主体の地域開発として位置づけました。住民運動と異なり、行政がその気になれば力がちがいます。まず県を通じて学者グループによる建築・造園・交通運輸・都市・地域計画等の諸分野に渉って学問的調査をおこない、その結果に基づく診断書によって、住民を指導しました。日本で始めての集落保存という大事業であっただけに強く団結した住民運動体の愛する会といえども、すべてを背負ってやりぬくことはできません。またこの事業のもつ特性として、住民の賛同がなければ事が運ばない。
行政力での推進にも自ら限度がある。文化財保護と都市計画、住みよい町からみて、専門的な学問も必要です。ですから住民と行政と学者の三曲合奏が望ましい姿でありましょう。行政に保存の意志なきとき、さながら大海を行く船に船頭なきが如く、学者の協力なきは羅針盤をもたずして船に乗るが如し。掛け声だおれで破壊は進んで行く。最後に笑うものは、保存に成功した者だけです。子孫のために残すべきものは残して置こう。
富田林の島居さんをご紹介します。本職はペンキの方のお仕事です。富田林寺内町を守る会の会長さんです。
富田林
富田林寺内町を守る会 鳥居 辰夫
富田林は通称河内の富田林、詳しくは太平記に出てくる金剛山の麓に存在する富田林です。建築物としては古く、室町の中期から江戸中期に建造されたそのままの家屋が40数軒ほど、所々に存在して水田との景観を残している町です。
会の名称は富田林寺内町を守る会ということになっていますが、現在のところはどのように守るかという課題にとり組んでいる段階です。
函館に来てこの公会常に入り、明治期のこの建造物と富田林に残された江戸時代の建造物のよさを比較しながらこの壇上で考えたことは、町並ゼミによって与えられた力というものは徐々に若い人たちの力に移行されている。富田林に課せられた問題は、寺内町に住む若い人たちの参加にある。400年も過去の中に、生活していても馴染めないという若い人たちの実態を見るにつけ、今後どのようにしていくべきなのだろうか。
小樽において、近江八幌において、若い人たちが町を蘇させた。その若い人たちの力を、寺内町の景観の保全のために、再度再度認識してもらうことを課題として、今後努力していきたいと思っています。
大平首相と同じ字を書くんですが、こちらはオオダイラと読みます。大平宿をのこす会の会長勝野さん。高校の先生で一昨日小樽の海で泳いだという大変な勇者です。
大平宿
大平宿をのこす会 勝野 順
木曾路は既に山の中である。という妻籠からさらに東の方へ山を登っていった山間盆地、そこに大平という集落があります。最盛期には戸数70戸を数えたが、例の高度成長の波をうけて過疎化が進み、45年には集団移住してからっぽになってしまった。その無人の集落を残そうと保存運動が始まって、今年で8年になります。
現在は民家を借り受けて住めるようにしてあり、一般の人々に利用してもらいながら、その利用費(自炊一泊1000円)と会員の会費によって補修保存されています。
全国にもこのような集落はたくさんあります。建築的価値は別として、庶民が苦労して生活してきた所であるわけで、これを保存する運動を全国的に広めていきたいと考えています。
活動を進めて意外に思ったのは、テレビも何もない所に家族と行って囲炉裏の火で煮炊きをする中で、便利な生活の中で、親子兄弟の間に、失っていたものを見出す場所として意味をもっていたということなのです。
全国でそういう話を聞いたらご一報ください。コンサルタントとして出かけて行きます。ご協力お願いします。
来年の会場になりました、琴平の位野木さんにお願いします。こんぴら門前町を守る会の会長さんで、有名なおまんじゅう屋のご主人です。
琴平
こんぴら門前町を守る会 位野木 峯夫
“金毘羅船々 追手に帆かけて シュラシュシュシュ……”
皆さん!全国津々浦々で歌われている民謡そのもの。金毘羅大権現というお宮を対象としているような、古い民語はここだけではないでしょうか。
そのように私たちの町、門前町琴平は、全国の皆さんによってつくられた、日本唯一の残された門前町であろうと信じています。従って私たちは、住んでいる琴平門前町を残すということは、日本民族の中に江戸時代から伝わっている心の拠りどころを残すことであるという、大きな誇りをもって取組んでおります。
琴平という所は、決して鉄筋コンクリートの高層建築によってつくられる町ではありません。壊される町ではありません。私たちはいま、高度経済成長の後遺症によって冒されようとしている町を、必死になって守ろうとしているのです。
いま大きなホテルが金毘羅さんの所に計画されようとしています。私たちは反対運動を展開しています。私たちの戦いの特徴は、私たち町人と外部の資本のごく一部の民間人との戦いです。行政はその中に入っておりませんが、町人同士の争いにかえって迷惑な姿勢をもっております。幸せなことに県の方が非常な力を入れてくれていることが、私たちにとっては救いです。
この私たちの戦いに対しまして、全国町並み保存連盟の仲間たちが、民族の遺産であるこの門前町を守ることについて大きな支援を与えてくださり、来年琴平で全国大会が開かれることになりました。
函館の皆さん、もし琴平へ来られる方がありましたら金毘羅大権現の絵馬堂に、今から約100年前の明治の初め頃、四国の金毘羅さんの近くの村々から入居して北海道に参った方々が寄進された絵馬がかかっております。昨年NHKがとりあげ、北海道のルーツを訪ねるということでテレビで放映されました。
昨日バスの中でご案内くださった大森先生は、ご先祖が近くの村から移民された3代目ということで、琴平とこの函館は、既に見えない縁の糸で結ばれています。
私たちは函館の皆さんが無緑のものとは思っていません。親戚のような気持ちでいますので、どうぞ皆さんお揃いで、来年の全国町並みゼミには、是非お越しいただきたいと思います。皆さんのお越しを心からお待ちしております。
社会面が終りまして論説に移ります。連盟の顧問で、京都大学名誉教授の西山先生にお願い致します。
町並み保存の意味
全国町並み保存連盟顧問京都大学名誉教授 西山 夘三
私は西山です。都市計画を研究しているものです。
町並み保存連盟では、現在20団体参加という話がありましたが、全国では200に近い数の歴史的町並みとして指摘されたり、歴史的環境を守る運動が起っている所があります。
これは高度経済成長期に、古いものはまずい、新しいものはよいとされた結果、全国画一の町になって来て、故郷へ帰ってみたら姿が変ってしまっていて、これではいけない 故郷を何とか残したいという、古いものへの郷愁といったものが出発点になったものと思われます。
しかしそれだけではない。よそから来て古いものを見て、ああいいなあと言う人が出てくる。そこに住んでいる人の中には、迷惑だ 実は古くて困っているんだという感覚の人もいるわけですが、言われて見れば日常は何とも思っていなかったものの中に、本とうのよいものを発見したという場合もあるわけです。
実は町並み保存運動というのは、大体こういう筋道をたどって、本とうにいいものを残そうではないか 私たちは祖先から積み重ねて来たものの上に生活しているのであって、これを無視して人間の生活は成り立たないのだ という自覚に連っていると思うわけです。
実際われわれは貧しい生活環境の中に住んでいるわけです。しかしその中でも、過去から珠玉のような遺産を受け継いでいます。これを何とか残したいという町並運動に見覚めた人が、各地に出て来ました。しかしまだ国民のもの、住民全体のものになっておりません。一つ一つの文化財を残すということはできますが、町並みは住民全体がそうしようというのでなければいけない。住民の運動が主体となってはじめて成り立つものなのです。
ところが住民の力だけでもできない。法的規制とか権力の裏打ちがなければ、当然完全にできるものではない。行政というのは住民の意向を受けて動くものです。自治体は住民のためにあるもので、住民が望むならそうしなければならないのです。法律がなければ、法律を作ってでもやらなければならないものです。
現在都市計画法という法律はあるけれども、必ずしも文化財を守る、歴史的環境を守る、という観点から考えると十分ではありません。かえてゆく必要があります。専門家、建築家の力をあおがなければならない。私たちは住民の方々の運動に、助力したいと思っています。
町並み保存策というのは、従来日本の町づくりの中に織り込まれてはいなかった。歴史的環境という根本の意味での都市計画づくりというのは、これから始まると言ってもいいと思うわけです。その意味で町並み保存連盟に非常に大きな期待をかけているわけです。
函館に来ましたら、歴史的風土を守る会を作っておられ、しかも非常にいいものが残っている。しかし残っている所は残念ながら開発の遅れた所、景気のよくない所が多いわけで、函館もご多分にもれずそういった点があります。
しかし、だから壊せというのではなく、それを入れながら新しいものをつくっていく。単に守るだけでなく新しい産業とか住民の生活を興す都市全体の性格を、どうつくっていくかという計画と一緒に進まなければいけない。
そういう意味で町並み保存運動というのは、将来の私たちの地域の生活を、よりよく創造していく大きな運動につながっていくものであります。皆様のご奮闘を期待したいと思います。私の話はこれで終ります。
ここに並んでおられるのは、われわれ仲間のほんの一部です。皆さん仕事を休み、旅費をため、同じような歴史的環境を守ろうという函館の皆さんとの連帯を意識してやって来られた。ご協力ありがとうございました。
最後にこの立派な公会堂を、われわれの会のためにお貸しくださった函館市に感謝の気持をこめて、函館の歴史的風土を守る会の田尻さんに閉会のご挨拶を。
閉会挨拶
函館の歴史的風土を守る会副会長 田尻 聡子
24日から始められました第3回全国町並みゼミ、今日で全部終了いたしました。4日間のハードスケジュール本とうにご苦労さまでした。
この函館集会にいらっしゃった殆どの方は、これから道内各地へ旅行されるご予定だったのですが、わざわざおいでくださった。函館に対する厚い思いと暖い友情に言葉もありません。ありがとうございました。
皆さんによってもたらされた、このエネルギーとこの知恵を、これからの運動の糧にして行きたいと思います。
来年までお元気で。金毘羅大権現の下でまたお会いしましょう。夫々の地でのご健闘をお祈りします。
近代建築北海道地区報告懇談会 文化的拠点造りによる文化開発を
5月27日 6:30 五嶋軒本店にて
大河内 憲司 ―函館―
建造物の保存について語られているが、若い人がその価値を認めていない所に問題がある。われわれが価値をとき保存を訴えても若い人の気持の中に古い物の中にある価値を大切にする心が浮び上ってこないかぎり無理なのだ。つまり文化開発ということだと思う。
価値判断は十才までにできあがる。現在空いている歴史的建造物を利用して、市内の各地区のミュニティの中に小学生のうちから物の大切さ、古い物の文化的価値を知らせ心の開発を計る文化的拠点を造ることを提案したい。
文化の大切さが伝わらないかぎり、歴史的建造物に建築的価値や歴史的意味があっても受入れられない。これが都市再生の戦略だと思うのだが…これに対するご意見をお聞きしたい。
(函館の歴史的風土を守る会)
陣内 秀信 ―東京―
私は建築史特にベニスの都市史を研究しているものだが函館の町が一目で好きになった。共通点があるのだ。函館は港町で窓として外に開かれ、いろいろな文化をそれぞれの段階でうけ入れて多様な文化をつくり上げているという話があったが、ベニスもまさに古代ローマ、ビザンチン、アラブ、ゴシックなどの文化をとり入れて独自の文化を形成した町だ。共に魅力的で知的好奇心を満足させてくれる。こうした地域なり町なりがもっていて積み重ね築き上げてきたものの一つ一つのおもしろさを見つめる心が、町への愛着のとっかかりになると思う。
開発という場合、拡大する新しいことをやることととられがちだが、自分たちが造り上げて来た長い歴史の伝統ある都市構造とか、生活構造、住居、人間関係など既成されている多様な価値をもった 都市とか地域の中にありながらわれわれが忘れているものを、もう一度ひき出して今後の町づくりに結びつけることが本とうの開発だと思う。文化開発というのもまさにそういうものだろう。
眠っている空間、もの、それを愛するメンタリティ、これは若い人にも通ずると思うのだが。
(東京大学)
足達 富士夫 ―札幌―
文化の拠点という話が出たが、いろいろな形が考えられると思う。施設というと建物をイメージするが、外部そのものを、オーケストラや新劇などの舞台として使うことも考えられる。西部にはそれにふさわしい雰囲気があるように思う。
”祭”というのは、地域を結びつけ、活気づける有効な方法だといわれるが、ともすると土着的な祭を考えがちだ。新しい祭を創造して町全体を舞台として使うというのも”ハイカラな函館”にぴったりだという気がする。
基坂を公園化して旧渡島支庁前の広場を整備して催しものをすることも考えられるのではないか。勿論騒音など住民との間で細かい検討は必要になってくるだろう。
(北海道大学)
石塚 雅明 ―小樽―
函館の皆さんに若い者としてお土産をさしあげたいと思います。小樽の青年会議所の方たちの試みなのですが故郷の道という題名で、山の中でするオリエンテーリングを、小樽の町並みを舞台に行ったのです。皆さんに渡されるのは建物の紹介が書かれた余白のあるカードで、これを持って指定されたコースに添って建物を尋ね歩くわけです。建物の前では係の人が、イラストのついたスタンブをおしてくれる。全コースで十何個かのきれいなスタンプが集まるので、子どもも大人も大よろこびです。
お天気がよかったせいもあって、小樽では3000人ほどの参加者があり、ふだんはひっそりした歴史的建物の並ぶ町並も、リュックを背負った親子連れで賑わい「小樽にもこんな建物があったんですね」というありがたい感想も聞かれました。
函館にもこんなに多くの歴史的建造物があるのですから、是非実現されふさわしい町づくりへのまずできることの第一歩としていただけたらと、お話したわけです。
(夢の街づくり実行委員会)
三ツ谷 毅一 ―函館―
暖かい友情につつまれながら、遠いこれから先までのわれわれの生まれて来た故郷を思う町並みゼミ。これからますます発展し、鋭い眼と暖かな愛情とで、日本中の町並みを守っていく大きな力となることを祈念します。
(函館市教育長)
文化的拠点を!! と提案された大河内先生の発言に関連して寄せられたご意見を、当夜の記録の中からまとめました。紙面の都合で割愛しました貴重なご意見に対してお礼とおわびを申し上げます。
卓上の色どりに加えて、心満たされた豊かな歓談でした。ご尽力下さいましたトヨタ財団、建築士会、町並み保存連盟、司会のNHK蕉木アナウンサー、そしてご参会の皆様に心からお礼申し上げます。最後は乾盃の三ツ谷先生のおことばで締めくくらせていただきました。(文責 岡田)
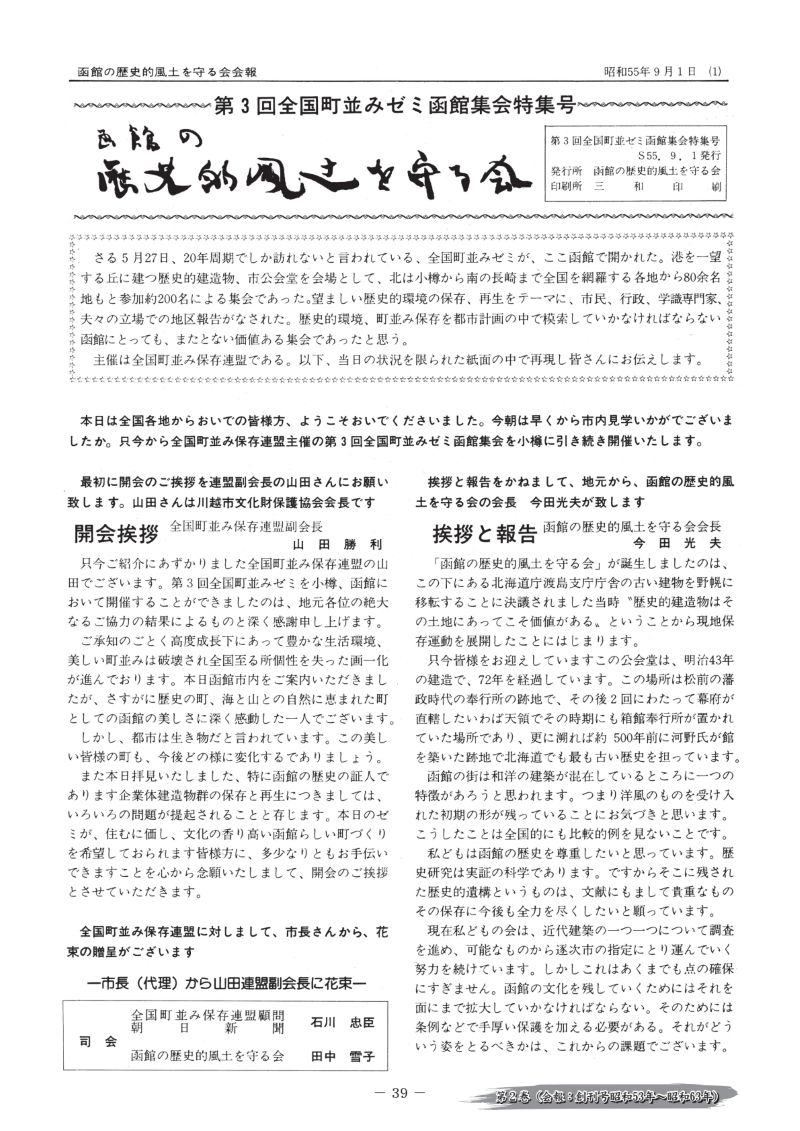


コメント