《第2回定期総会より》―会の真価を発揮する二年目に―函館の街づくりをどのように進めるか
函館の歴史的風土を守る会の第2回定期総会が去る5月27日、五嶋軒本店で78名の会員の参加のもとに開かれ、昭和53年度事業・決算報告並びに昭和54年度事業計画・予算・会則の一部改正等が承認された。
総会は、田尻副会長の開会のことば、今田会長の昨年度をふりかえっての挨拶に始まり、函館市社会教育課長佐藤健治氏より「旧渡島支庁々舎保存決定・都市計画公園(元町公園)の計画化・公会堂修復決定は函館の文化財を守る気運を高め強い位置づけをした当会の刺激があったればこそ」との祝辞を受け議事に入った。
工藤事務局長より昭和53年度事業報告・収支決算報告があり、昨年度の質的に高い活動実績ときわめて正確な会計が全参加者の拍手によって承認された。続いて、昭和54年度事業計画の概要が53年度事業をふまえ提案、討議された。「当会の活動は最終的には保存活動となるのだが、そのためには啓蒙活動に一番力をかけるべきである。地域住民に浸透していくような啓蒙が成功すれば、おのずと自然な形で文化財が守られ保存される」(近藤会員)「今こうしている間にも、亀田市役所の石碑など文化財が失いかけている。このようなとき当会はどのように動くのか」(宇野会員)「小樽運河を守る活動への支援を」(桜井会員)等の発言がなされた。今田会長から「西部街なみ保存について将来の条例化を予想し会員外の地域住民等も含んだプロジェクトを結成し、住民感情を取り入れた研究に着手したい」旨が強調された。昭和54年度予算について井上会員より大口寄付等の質疑があり「当会では会社からの寄付には慎重に対処し原則として個人の浄財を充てる」旨の再確認がなされた。道教委よりの補助金15万円は特別会計予算に計上、調査研究研修会小冊子印刷費等に充てることが承認された。さらに会則の一部改正が提案され、各称の附加、顧問制等が承認、会長より顧問に近藤元、真崎宗次、須藤隆仙各氏が、運営委員に奥平忠志、大河内憲司、木村訓丈、木村登美子、高坂柳好、中村雪子の六氏が委嘱された。
その他、会員から朝日新聞木原氏のルポの反響、他都市機関との連携、自治協会報告についての質問(千葉会員)元町公園・湾岸道路について今年度会の課題としたい(大河内会員)地域住民の声がよくわからないので調査を(石塚会員)等の発言があり、これら提案事項は運営委員会に具体的活動計画の審議が付託された。最後に和泉副会長の「熱意あふれる討議に心強さを感じると共に、今年こそ会の真価が問われる」との閉会のことばで総会を閉じた。総会後、小樽運河を守る会々長峰山ふみ氏より感銘深い活動紹介があり、更に松前町史編集室長榎森進氏より函館・箱館商人の存在理由と成立要因を日本経済史の立場から解明した講演があり感銘を受けた。
榎森進先生講演要旨
1〈松前藩の性格〉江戸時代の幕藩体制の基礎は農民からの米などの現物徴税であるが、松前藩はアイヌ交易権に基く漁業収奪と入出船舶資本及び商人への課税収入を基礎として成立していた。その商人とは松前・江差港で活動した船所有の近江商人で敦賀・小浜を基地とした(両浜組など)ギルドであった。
2〈北前船〉日本海を航路とする松前交易に従事した買積船(船主+商人)なる特殊性格をもつ。これは近江商人の衰退と共にその支配より脱し発展したもの(商人資本及び流通の変質)。
3〈幕府の東蝦夷直轄と函館港〉この北前船は、東蝦夷地の幕府直轄を機に顕著となり明確となる。函館港はその基地となる。かくて近江商人の没落と高田屋嘉兵衛を中心とする函館商人の登場となる。
4〈日本経済史と函館港〉これらは、鰊肥料市場の日本における発展、大阪の仲買商人資本の発展に条件づけられているのである。(具体的内容は次頁へ)
《総会特別記念講演より》近世箱館の商人の活躍―その舞台と背景―
日本歴史学研究会々員・松前町史編集室長 榎森 進
近世の箱館といえば、“函館っ子”なら、誰しも高田屋嘉兵衛の名を思い起すにちがいない。確かに、近世の箱館にとって、高田屋の存在は大きかった。特に寛政11(1799)年の幕府の東蝦夷地の直轄時から天保4(1833)年の高田屋の没落に至る35年間の箱館の経済は、高田屋の動向を無視して語ることはできない。
しかし、高田屋の箱館での活躍期間がわずかに30数年であることからも判るように、近世の箱館の経済や商人のあり方を高田屋のみに代表させて語れないこともまた明らかである。そこで、ここでは、従来あまり注目されることの少なかった株仲間問屋商人の動向に焦点をあてながら、近世における箱館商人の性格などについて若干ふれてみよう。
◇ ◇ ◇ ◇
箱館は、その昔“宇須岸”といわれ、室町・戦国期頃には蝦夷地随一の昆布の移出港として栄えていたことはよく知られている。しかし、康正2(1456)年~長禄元(1457)年のコシャマインの蜂起や永正9(1512)年のアイヌの蜂起によって同地近郊の諸館が落城して以来、箱館は寒村と化した。また、松前藩成立後は、亀田番所が置かれ、東在支配の拠点として位置づけられるものの、藩の経済を支えた初期特権商人(主に近江商人)が城下に出店を設け、また蝦夷地産物の大部分が松前に回漕された近世前期にあっては、箱館の経済的地位はすこぶる低かった。 この地が松前三湊(松前・江差・箱館)の一つとして経済的に重要な位置を占めてくるのは享保・寛延期以降のことである。それには次のような事情があった。まず第1に、元禄頃から汐首岬を越えて噴火湾沿岸に出漁する漁民が増加する一方、戸井から野田追に至る蝦夷地の各場所(箱館六ヶ場所という)の経営を箱館商人が請負い、そのため、こうした地域の産物が箱館に集荷されるようになったこと、第2に、これによって箱館を媒介とする商品流通が活発になり、そこに介在する問屋商人が急速に成長してきたこと、の2点である。つまり、ヒンターランドの拡大に伴う商品流通の発展と問屋商人の成長、この二つがこの期に箱館の経済的地位を上昇させる大きな要因になったのである。
しかも、ここで注目すべきことは、延享5(1747)年藩側の強力なテコ入れもあって、これら問屋商人の多くが株仲間問屋として組織され、出入商品の一手取扱いの特権を与えられるとともに、本来藩の行政機関が行なうべき出入商船の取締や諸役銭(税金)の徴収業務をも代行させられることによって、一挙に藩権力と密着した特権問屋へと成長していったことである。この時、問屋株を許可された商人は、長崎屋佐藤半兵衛、浜田屋井口兵右衛門、秋田屋芦野喜左衛門、若狭屋荒木宗太郎、亀屋蛯子武兵衛、角屋榊吉右衛門の6軒であった。(幕末には10軒になる)また同じ時期に鍋屋吉村吉右衛門はじめ16軒の小宿株が許可されている。こうして、享保・寛延期以降幕府直轄時までの箱館経済は、こうした株仲間特権問屋・小宿商人の動向を軸にして動いていくことになるのである。しかし、蝦夷地での経済圏がせいぜい渡島半島東部地帯のみであり、また有力場所請負人の大部分が城下に店を構えている中では、経済力に於て松前との間に依然として大きな開きがあったことも否めない。
ところが、寛政11年の幕府による東蝦夷地の直轄は、こうした箱館の経済や商人の動向に一大転期をもたらすことになった。すなわち幕府は東蝦夷地の幕領化に伴い場所請負制度を廃止して、直捌と称して幕府自らが漁場経営にのり出し、しかも、松前藩と直結した旧来の近江商人を排除し、天明期頃から蝦夷地に進出して来た伊達林右衛門、栖原角兵衛などの江戸系商人や高田屋嘉兵衛などの新興商人を積極的に登用し、東蝦夷地の産物を半ば強制的に箱館に回漕させた上で、大坂、敦賀、江戸などの主要港に回漕させるに至ったのである。その結果、箱館は単なる箱館近接の蝦夷地(旧六ヶ場所はこの期に村並になる)産物の集荷地にとどまらず、南千島を含む東蝦夷地の中心的な集荷地へと急速な変貌をとげ、移出商品の性格も、従来の昆布中心型から昆布を含むあらゆる海産物へと変化していった。高田屋の豪商としての成長もまさにかかる条件の中で実現されたものであったが、前記の株仲間問屋商人たちもこの期の商品流通の飛躍的発展をテコに着実にその力を増大させていったのである。
その後、文化4(1821)年の全蝦夷地の幕府直轄、同9年の直捌の廃止、文政4(1821)年の松前藩の復領という政治経済的変動を経る中で、蝦夷地産物の多くが再び松前に回漕される傾向を生むなど経済的に少なからざる打撃をうけたものの、幕領期に高田屋はじめ藤代屋、和賀屋、浜田屋などの場所請負人が台頭し、かつ間屋商人が東蝦夷地産物の箱館回漕を強力に主張したこともあって、その打撃を最少限にくいとめることができた。また高田屋没落後は杉浦嘉七、小林重吉などの場所請負人が成長してくるが、先の和賀屋、浜田屋が株仲間問屋の一族であったところからもうかがわれるように、問屋商人の力は非常に大きかったのである。したがって、近世箱館の経済をその基底部で支えてきたのは、株仲間問屋商人であったと、みることも可能がもしれない。
「街並みゼミ」と「全国町並み保存連盟」
全国町並み保存連盟顧問 石川 忠臣
「皆さんコンニチワ! 私、函館におりまして、本当に近江八幡を北から愛をこめてながめていたわけなんです。と申しますのは、函館と近江八幡は近世の頃から北まえ船を通じてゆかりの地であったわけで……」。田尻聡子さんの報告が、近江八幡市のま新しい文化会館の満員の会場に美しく響きます。去る6月23・24日に開かれた第2回「全国町並みゼミ」のーコマ。あの独得な“田尻節”はゼミでもすっかり有名になりました。なにしろ田尻さんは、小樽運河を守る会の峰山女史とともに、わがゼミの誇る“紅二点”なのです。
さて、このゼミの主催者は「全国町並み保存連盟」といいます。49年4月、「郷土の町並み保存とより良い生活環境づくり」をモットーに、有松まちづくりの会(名古屋市)、妻籠を愛する会(長野県)、今井町を保存する会(橿原市)の代表が集まって結成されました。小なりといえども、民間初の全国組織。だが正直にいうと、カネも力もない、かといって“美男子”とも思えない団体でした。しかし、事はやろうと思えばやれるものです。53年はじめ、予算ゼロで第1回「全国町並みゼミ」を計画し、実行したのですから。話は、こうです――。
50年に文化財保護法が改正され、歴史的町並み問題がだんだん具体化していくうちに、勉強しなければならないことがヤマほど出てきました。それぞれの地区ごとに悩んでいるより、仲間同志集まって、いっしょに話合おう。これが町並みゼミの出発点となりました。そして、連盟の事務局のあった有松町と、その後加盟した「足助の町並みを守る会」(愛知県)に会場とゼミの具体化をお願いしました。連盟は団体加盟で個人会員はいません。そこで住民、自治体、研究者ら歴史的環境間題に関心ある人すべてに門戸を開くことと、スポンサーのいない、“手弁当で集まる”ことをモットーにしました。
だが、初の試み。何人集まるか、フタをあけるまで胸はドキドキしました。結果は――。全国30地区から220人と地元から約500人が参加、出席者の熱意と地元の献身的な協力で成功裡におわりました。とくに話合いの結論として「町並み保存を中心とする地域の創造の主体は、住民であり、自治体であり、それに協力する専門家である」と宣言し、三者の関係を正しく位置づけたことは、大きな収穫でした。ともすれば、自治体と対敵するのが住民連動だと思ったり、運動の主体を学者にまかせきったり……。そんな風潮に大きな影響を与えたようです。
ことしの第2回ゼミは、有松・足助ゼミの成果の上に開かれました。ことしの特徴は、全国からの参加者が倍増し規模がぐっと大きくなるとともに、実行委の中心が近江八幡青年会議所というように参加者が若返り、顔ぶれも多彩化し、運動が多様化したことです。これは日本の歴史的環境運動の急ピッチな進展ぶりを見事に反映しているようです。ゼミの雰囲気や詳細な討議については、田尻さんからお聞きになるか、『環境文化』誌41号(ゼミ特集号)を参照して下さい。
さて全国町並み保存連盟は、ことしのゼミで8地区が入会し、加盟住民団体は全部で18となりました。前記の4地区を除いて列記すると――富田林寺内町を守る会(大阪府)、奈良井宿保存会(長野県)、よみがえる近江八幡の会(滋賀県)、こんぴら門前町を守る会(香川県)八日市周辺町並み保存会(愛媛県)、川越市文化財保護協会(埼玉県)、祇園新橋を守る会(京都市)、伊勢河崎の歴史と文化を育てる会準備会(伊勢市)、小樽運河を守る会、小樽夢の街をつくる実行委員会、大平宿をのこす会(飯田市)、城下町彦根を考える会、会津北方風土会(喜多方市)、会津復古会(会津若松市)。
残念ながら、この中には「函館の歴史的風土を守る会」の名前がありません。函館市民の歴史的環境運動のユニークさには、私たちは、敬意とともに大きな関心を抱いています。近い将来にはぜひ連盟に加盟して、その豊富な経験を全国の仲間たちに知らせて下さい。また、来年の第3回「全国町並みゼミ」は、小樽で開かれます。せっかく北海道まで足をのばすのなら、帰りには全員で函館に寄り、町並み見学とともに記念集会を開こうかと案を練っているところです。その節はよろしくお願いいたします。
大会での雑感…
副会長 田尻 聡子
町並み保存連盟顧問の石川氏は会報3号にご執筆下さった木原啓吉氏と共に大朝日を支えるギャーナリストです。木原氏が狂乱怒濤の高度成長期の最中より今日まで歴史的環境保存も含め一貫して環境問題に警鐘を打ちならされ、石川氏は全国町並み保存連盟と言う実践的運動体を作り育てあげた方である。マコト世の木鐸と言える新聞人よと改めて胸を打たれました。
―歴史的環境は、地域の個性と文化を表現する基本的な要素であり、地域に誇りをもつ住民の精神的連帯のシンボルである。これらは住民と自治体が協力して保存・再生し、さらに創造すべき公共の財産である―近江入幡宣言こそ、参加者全員の願いであり祈りであったと思う。
《足達研究室からのレポート》函館西部地区の町並み
北大工学部教授 足達 富士夫
*去る8月4日市公会堂における講演会より*
多くの町がせっかちで無計画な「近代化」のために個性をうしなって、町のいわば氏素姓がわからなくなってきているなかで、函館の町はまだはっきりと自分の顔をもっている。
元町や弥生町のあたりをあるいていると、ほかの町のどこでも見かけたことのない、この町にしかない町並みをあるいているという実感がある。そういう町の個性をつくりだしているのは、独特の形をもつ民家群や、そのなかに混って点在する、いかにも函館の繁栄の歴史を象徴するような、重厚で古めかしいビルのならんだ町並みである。
観光案内をのぞくと、まず例外なく五稜郭、ハリストス教会、トラピスチーヌ、外人墓地などが列拳されている。いずれもわが国最初の開港場の一つとして、欧米の文物に直接ふれながら発展してきた函館の歴史をそのまま表現している史跡で、ほかの町ではめったに見られぬ貴重な文化貴産である。しかし、観光案内をたよりにこれらの「観光名所」をおとずれる観光客はたぶん気がついてはいないが、案内にはとりあげられていないこの独特の町並みのおかげで、実は観光名所が生きているのである。
町並みの特色をつくっているのは、第1に和洋折衷の町家である。函館の人ならだれでも知っている。あの下見板ばり2階建の住宅――2階がタテ長の洋風窓で1階がタテ格子のはいった和風窓(1階も洋風のものもある)の住宅は、函館とその近在の独特の住宅形式である。寄棟の屋根は庇が壁から直角につきでた肘木でささえられたるきている。こういう庇は、棟から下ってきた極で庇をささえる和風のやり方とはちがっている。1階と2階との間の胴蛇腹の装飾なども洋風の特徴である。
こういう外観にたいして、内部はたいていの家が純和風である。つまり和と洋の混合が外観だけでなく、外観と内部との間にも見られるのである。こういう和と洋との結合がどういういきさつでうまれたものかはわからないが、おそらくただの「上等舶来」の風潮のあらわれではなく、積雪寒冷の気候条件も考慮して、工夫をかさねてつくりだした独自の住宅形式であろう。洋風の上げ下げ窓や開き窓は、和風の大きな引違い窓にくらべて、はるかに気密で防寒性能がすぐれているのである。
ところでこの町並みの特徴は、そういう独特の民家のあることだけではない。洋風町家のほかにも和風の町家や邸宅があり、土蔵づくりがあり、さまざまの様式の住宅が混在している。それにもかかわらず町並みの姿が混乱におちいらず、まとまりとおちつきをもっている。これが第2の大きな特徴である。
この特徴は、いろんな様式の建物の混在がそのまま風景の混乱をまねいているたいていの現代都市ともちがうし、同じ様式で統一されているおかげでまとまりが保たれている倉敷や高山などに見られる古くからの町並みともちがう、全くめずらしい町並みである。めずらしいだけではない。現在の都市では建物の様式などということはもう望むべくもないが、それでもこの町並みのように、建物の高さや全体の形がおおむねそろっで、ゆたかな緑が適切に配置されるなら、現代の都市でも町並みの景観をととのえることはできぬことではないという貴重な示唆をあたえてくれるようにおもわれる。
ところで、いくらすぐれた町並みでも住みにくいのではなんにもならない。
西部地区は、実は生活環境として多くの欠陥をもっている。第1に古くて冬寒い家が多い。元町、弥生町あたりでは7割以上が明治・大正期の建物だからあたりまえであるが、これを改善しなければならない。第2に建物がたてづまって空地がすくない。弥生町の一部はことにいちじるしい。そのほか交通(步道、駐車場)、下水道の整備も必要である。商店や病院などの生活施設は充実しており、地区全体の評価は高い。100年の蓄積はなんといっても大きいのである。
この地区を将来どのように考えたらよいだろうか。生活環境整備のための再開発はいずれにしても必要である。しかし現在除々にすすんでいるばらばらの無秩序な再開発も、中高層化型の再開発もこの地区の特色を台なしにしてしまうことはあきらかである。かといって、建物の外観の保存、修復を中心としたいわゆる町並み保存もこの地区にはなじみにくい。老朽狭小でしかも寒冷地むきでなく、すっかり建てかえてしまう方がよい街区もあるからである。
ここでは環境整備をすすめながら、その中で特色を維持するという考え方をとるのがよいとおもう。具体的にいうと、公会堂、旧渡島支庁舎、などの文化財的建造物は完全な保存をはかり、住宅は原則として改築、改修をすすめる。その際、建物の高さやおおよその形は周囲の町並みにあわせて一定の基準をつくる。また維持状態のよい民家は防寒改修をほどこして(これは最近では比較的かんたんにできる)外観の保存をはかる。老朽・狭小地区は屋根や窓の形を考慮しながら2~3階の集合住宅にたてかえる。こういうゆるい規制で環境改善をすすめながら町の特色を維持することは十分に可能だと思う。そこにまたこの町の特色があるのである。
また基坂や二十間坂のような広い坂は、ただの道路でなく公園兼用に整備して歩道や広場の充実をさせ、同時に海岸との一体化をはかる。こういう「坂道広場」や海岸や寺の境内などを使って、夏の数日間、音楽、演劇、野外美術展などの総合芸術祭を開くといったことも考えられるのではなかろうか。町全体を、アマ・プロいりまじっての全国規模の芸術祭の場にするのである。この町はそういう祭の舞台にふさわしい雰囲気をもっている。
町並みというのは個々の住宅とちがって、一見住み心地に関係がないようにみえるが、それば市民全体の文化の蓄積の表現であって、すぐれた町並みは一朝一タにはできない。まして西部地区は函館を象徴する町で、市民の9割までがなにかの形でのこされることを期待している。が、現実は期待とうらはらに、町並みがどんどん変化している。市民と市当局による整備方針がすみやかにたてられて、変化を適切に誘導していけるような措置が一日も早くとられることを期待したい。
歴史の散歩 シリーズ4 ~元町界隈の石畳~
(仮称)学校法人葵学園函館あおい幼稚園々長 田畑 繁雄
8月末のある日、西部の石畳の坂道を足の向くままに散歩してみた。
かってNHK放送局があった南部坂は、道の両側にアスファルトが被せられ、幅3メートルほどの中央部分だげに、荒れた石畳が侘しい顔をのぞかせていた。
元町配水池の前を通り、二十間坂から大三坂へ向かう。ポプラ並木を渡る風も、教会の尖塔の上を流れる雲も、もう秋だ。坂を横切るたびに、眼下に開ける港の景観が変わり、横津の山並みの稜線も変わる。遙か坂下を、時折小さな電車がちらりと見えては、家並みの陰に隠れる。ふと、タイムトンネルを抜けたように少年の日の光景が蘇ってきて、オーバーラップする……。
大三坂の上にあるハリストス正教会は函館の顔とも言われて有名だが、もう一つのハリストス教会はあまり知られていないらしい。松前藩戸切地陣屋跡(清川陣屋跡)へ行く途中の道沿いに、小さな有川ハリストス教会がひっそり建っている。明治7年、3名の信者から始まったという。祭壇の正面にイコン(聖像画)画家山下リン―~~聖ニコライの奨めに よりペテルブルグに留学~~の描いた“最後の晩餐”が飾られてある。この教会の信徒たちの墓地が、陣屋の奥約1キロの杉林の中にある。木の十字架と墓碑、合わせて60基ほどの静寂な墓域が、訪ねる者に無言で歴史を語ってくれる。野崎墓地の呼名は厨川司祭がつけられたとのことである。
基坂には、昔のような美しさが今はもうない。瓦屋根と白亜の瀟酒な英国領事館、ユニオンジャックがはためいていた。石畳の扇形に組まれた線も鮮かだった。バルコニーのある。木造のはいからな税関の屋根越しに、港が光っていた。子供心にも、見たことのない外国の風景を想像し、なんと美しい坂だろうと、誇らしく思ったものだ。
いま、石畳はみんなくたびれてしまって、どの坂も老醜を晒している。あの頃の美しさを取りもどす術は、もう無いのだろうか。“異国情緒豊かな歴史の街はこだて”のキャッチフレーズも、これでは泣きたくなるだろう。石畳の歴史を詳しく知っている人も見当らない。専門家に尋ねても諸説があって、さだかでない。 函館区史など、二、三の文献に目を通したが、石畳の記録を見つけ出すには至らなかった。
石畳の復元は、アスファルト舗装に較べて工事費が5~6倍もかかるという。道路としての機能だけを重視し、工事費を低廉に押えようとすれば、いきおいアスファルト舗装を優先したくなるのが常識であろう。でも、現に横浜市などは石畳の復元を実施しているという。要は、市民の関心と熱意にかかっていると言えそうである。
たまたま、“豊がさも、くらしやすさも、道路から”というキャッチフレーズを見た。最近、北海道開発局が出した、「道路を守る月間」のポスターの文案である。
道路の生命は住民生活の利便だけでなく、地域住民の生活に〈豊かさ〉をもたらすところにあることを、このポスターは訴えていると理解した。
“小樽の若者たちとともに”
小樽運河を守る会会長 峰山 ふみ
第2回ポートフェスティバルは7月7・8日運河周辺を舞台にくり広げられ昨年を上まわる10数万の人出をよび盛会のうちに終った。5月頃より毎週町内会館で50名ほどの若者達が集り準備を重ねた。資金づくりにシンボルマーク入りのTシャツ、手拭を売り又会場設営に夜を徹する努力をした。今年は「子供からお年寄りまで参加」をキャッチフレーズにユニークな催しがなされた。
運河周辺にはりめぐらした電線に紅い提灯が無数にともり8個のサーチライトにてらし出された倉庫が夜空にくっきりと美しかった。出店も百数十軒、手づくりの品をもちより軒を連ね、艀の上ではビアガーデン、ロック演奏、運河の歌など運河周辺は熱気につつまれた。保存か埋立かに揺れている中でこのような祭りでこのところに多くの人々を集めることが出来たのは何よりであった。
私共守る会も森本光子絵画教室や小笠原克文学散歩、忍路鰊場の会による沖あげの状況再現など協力又、守る会コーナーを設け運動のPR、署名活動をした。東京から「愛する会」の委員がかけつけピラを配布してくれた。署名をよせた34名の人々は口々に保存をねがいはげましのことばをよせてくれた。
この祭りを運営したのは運河保存団体の一つ、夢の街づくり委員会の若者たちや近隣の若者で、自主的な手づくりの祭りというのでエネルギーを発散し、もり上げた。全員が運河保存という意議が統一されてはいないかもしれないが、とにかくここでやる祭りのすばらしさを思う程にこの周辺の価値を再認識しだようであった。勿論市民はこの祭りの場を六車線の道路に変貌することをこの場に立って実感として感じとってくれたようである。
私共守る会も単に運河と倉庫群が残れば事足れりというのではない。実に利用され市民の生活にかかわり生かされていくことをねがっている。
最近、若い人々が小樽に住むことによろこびを見出してきている。ふるさと再発見の意識が強まってきた。先人の遺したすばらしい遺産を見通しこれを互に認め合ってこれを生かした街づくりを一緒にやりたい。文化はながい時間をかけみんなで考え、そだてはぐくみ、い(愛)とおしんでつくりあげていくもの、そのためには、長い時間をかけねばならない。運河保存運動も私共の世代から次の世代にかけての長い流れの中で実っていくむのであると思う。そのためには若者との連帯が 必要である。
年毎にこの祭りがいよいよ盛んになるように是非にもこの運河は残したい。実にこの地区が市民のくらしに生きづく保全のすがたをみんなで考え、小樽の個性がいよいよ生彩をはなつよう若者と一緒に働いてゆきたい。
やませ 「会の攻勢策が望まれる」
会員 宇野 均
「あゝ、オクチですか」―。来函当初、念を押すように聞かされた言葉である。札幌が未開の“奥地”に聞こえて大変興味を持った。
この九月で満三年になる。北海道、あるいは日本の「文化発祥(しょう)の地」という自負から生まれただろうこの言葉からかって栄華をつくし、文化に培われたプライドが伺えて頼もしいと思ったが現在は否定的である。
今日、歴然と(東京に対し)大阪が。“上方”と言うのに札幌を奥地と呼ぶ意気を持てないのはなぜなのか。優れた風土性を持つ函館が偉大な文化遣産などを無残に摘み取ってしまっているのが現状では仕方あるまい。
会が発足して一年を過ぎたがその間だけを見ても多くの物を消してしまった。五稜郭城しゃへいの松(道新横)、旧亀田市庁舎、旧戸井線橋脚(国道五号線)、旧税関倉庫(海上自衛隊内)、旧商船学校(弥生町)、庚(こう)申碑(湯川)などが姿を消したがこれらの他にもあるだろう。次には市役所、少年刑務所などが予定されれいる。紙幅の関係で物件のコメントは省略するが何でも古い物を保存すべきと云っているのではない。
隣りの上磯町山中で、「箱館戦争の台場跡」を発見?その後の調査で松前線工事の爆薬庫跡に落着いた。それならばと壊わしてしまったそうだ。我々は後世に何を残せるだろうか、せめて現在まで残った物だけでも中継することこそ義務と思う。
保存問題は難しい。金でも解決しないし、自治体がやるべきものと云ってみても現実性がない。やっぱり会の積極的行動こそがけん引力になると信じている。世論を喚起するために観光土産を開発したり他にも営利の事業などをしながら啓蒙する。また、消滅、破損、流出や新たな発見など、これらの通報を受ける「文化財一一〇番」のような制度ぐらいは市にさせて、その情報は市広報、当会でも欲しいなどと日頃考える事も多い。次代、“奥地”の人も存在する文化の証(あか)しに感心し、多くの糧を得るだろう。
―北海道新聞函館支社 報道写真記者―
いのちある教材の街
道教育大学函館分校教授・赤光社芸術協会委員 若林 繁雄
地域に根差す教育に関心を持ってから随分久しいが、小・中学校を訪ねる毎に考えさせられることがある。校長室にはきまって歴代校長の肖像が飾られ、メーンの壁面には校訓が掲げられている。それぞれに伝統ある学校の教育指標と歴史を象徴するにはもっとも端的なパターンとして恒常化されてのことであろう。中には賢者の格言や教訓を別に掲げて特色を添えている例もあるが、概ね子供を主体とした全国共通の基本的教育指標に留まっており、いまだ地域に根差した校訓に接したことはなく疑念を抱いたままである。もう一昨年になるが、旧渡島支庁舎移転の如き問題が起きるといまさらのようにその感を深くするのである。
―いささか我田引水の横みちにそれるが、あの移転が報じられた当時、美術文化を担う赤光社の私たちにとっては文字通り、青天霹靂の衝撃であった。文化財を愛する使命感から取るものもとりあえずニ回に亘って、市民の署名と保護の為の浄財を募るべく街頭に立ち上ったことである。幸いに心ある市民や団体が陸続と賛同され、やがて、これら民意の結集に挺身される人々の貴重な努力によって、翌53年4月には「歴史的風土を守る」当会が結成されるに至った。推持、啓発等の諸問題は今後に残されたが、庁舎移転については一応ことなきを得たわけである。―
余りにも目まぐるしく変る時代の波に溺れてしまう現象を理解しないわけではないが、新しい街づくりと称し遺構を棄捨するに等しい所行は、私たち自身の心を失うことにもなろう。地域住民としてこのような恥ずべき問題を惹起することは、住民一人一人が持つべき郷土愛、歴史的理解、遺構 等に対する価値観の欠除に起因していることは明らかである。そしてこれらは一朝一夕にして身につけられる性質のものではなく、結局のところ親の躾を含めて教育にまつよりないものと考えている。改めて言うまでもないが、地域にはそれぞれの歴史があり、すべて先人の手によって現在の街が存在し、そこに私たちが在る故に、営々として築上げここに至らしめた先人はもとより、偉業もまた、その証しとなる遺構も私たちにとっては、切ってもきれない血の連なりがあると言っても過言ではない。一体教育の場ではこのことを、どれだけ説き伝えているのであろうか。子弟をこの地域に育くもうとするならば、おそらく先人も望んだであろう心豊かな幸福に満ちた真の人間的生活の営みを、史跡や遺構を通じて説くことにより、どんなにか、彼等は生に対する心の糧となる郷土愛と誇りを持ち、畏敬の念はもとより、先人や遺構に対しても価値判断を正しくすることであろう。さらには、自己や自己以外に向ける創造的野心さえも期待できるのではなかろうか。駄足ながら、母校である中学校の講堂には、その地から出て江戸末期の維新に君臨した先人の遺影と説かれた道が掲げられていた。それは私にとっていまだに生への支えとなっている。函館はこの例にこと欠かない、いのちある教材の街である。
西部街並み保存のプロジェクト推進のために
運営委員 奥平 忠志
北大足立研究室の研究、自治省の報告など、近年西部の歴史的遺産の保存についての研究報告は、いずれも個々の建造物(点)の保存からエリア(面)の保存を強調しており、本会が指向する“西部の街並み保存”と一致する見解を提示している。その意味で、本会が具体的に“西部の街並み保存”の運動を展開する際の強力な理論的な裏付けを確保したと言えよう。
ところで、こうした一連の研究、報告は、住民の意向調査を踏まえた提言ではあるが、住民一人一人の意向を完全に消化した上での具体的、実践的な提言ではない。“西部の街並み保存”は現在の景観の保存を意味するものではなく、歴史的建造物との調和のとれた景観の、確立を意味するものであるから、Preserve(保存)とrenewal(再生)をの2つの目的を達成するものではなくてはならない。しかも、この2つの目的を達成する第1の条件は、保存する地域の住民の積極的な賛意と協力が得られることである。第2の条件は、第1の条件が充たされた上での財政的な裏付けである。例えば、保存建築物に指定された所有者への保存のための資金保障再生のための資金の裏付けなどである。
本会の役割は、この中の第1の条件が充たされる運動を展開することにある。保存されるべき地域に住居をもたない市民が、声を大にして、“西部の街並み保存”を叫んだとしても、それは犬の遠吠えにしかならず、積極的な実りのある運動とはなり得まい。本会の会員一人一人が西部の住民との対話を深め、その中で住民の意向を反映した街づくりのプランがねられるように自治体への働きかけが必要となろう。生活している住民の意向の反映されない街づくりでは、住民の同意が得られないどころか、本来の目的である“西部の街並み保存”は空論に終ることになる。
今後本会では、少人数のプロジェクトチームを中心にして具体的な運動の方法の検討、街並み保存条例の案文の作成などの研究を進め、全会員の協力を得ながら、着実に“西部の街並み保存”の運動を展開してゆきたいと考えている。会員、市民の皆さんのブロジェクトチームへの要望、意見をお寄せ下されば幸いです。
あるふあ
(1) 『函館今日から明日へ』―自由時間都市像をめざして― 著者 大野和雄氏(函館大学教授)
※内容は美しい函館の明日を提唱し、氏のこれ迄の研究成果及び実践例を 210頁に亘って掲載されている。
実費頒価1,500円 申込先(事務局)(田尻)(田中)
(2) 『箱館 高田屋嘉兵衛』編集責任者須藤隆仙氏 発行 高田屋嘉兵衛顕彰会・出版委員会
※内容は海運・造船等の偉業を成し遂げ、国後・エトロフ間航路と漁場を切り開き、日露紛争解決に尽力した高田屋嘉兵衛のすべてが50頁に亘って紹介されている。非売品だが残部が少々あるので会員のみ実費頒布する。
実費頒価500円 申込先上記に同じ
会のあゆみ <54.4.1~54.9.14>
・4.9 会報第3号発送
・4.14 全国歴史的風土保存連盟総会<開催地鎌倉市>
田尻聡子副会長・川嶋龍司運営委員参加
・5.2 第5回運営委員会(総会諸準備について)
・5.7 事務局会議(53年度決算・54年度予算について)
・5.16 事務局会議(53年度決算・54年度予算・事業計画等についての打合せ)
・5.20 第6回運営委員会(総会提出議案審議)
・5.27 54年度・第2回定期総会開催(五嶋軒本店於)
・記念講演「近世箱館の商人の活躍」 榎森進氏
・小樽運河を守る会の現状 峰山ふみ氏
・5.30 函館市文化団体協議会総会開催
今田光夫会長・工藤光雄事務局長・出席・理事に今田光夫会長推薦される
・6.4 事務局会議(新年度事業実施について打合せ)
・6.8 第7回運営委員会(新年度事業計画について)
・6.23~24 第2回全国町並ゼミ大会<開催地近江八幡市>
24日田尻聡子副会長参加
・7.7 日本青年会議所<JC>第28回北海道地区会具大会於<開催地函館市>奥平忠志運営委員講師に田中雪子運営委員パネラーとして参加 テーマ「文化と経済が調和したコミュニティー」
・7.11 建築家「ざっこの会」於今田光夫会長講演する。 テーマ「古建築物の保存について」
・7.15 本会四女史、佐々木正子運営委員・田尻聡子副会長・田中雪子運営委員・藤田郁運営委員は、フリールポライター宮島郁子氏の取材を受け8月3日付社会新報“あすをひらく女たち”に掲載される
・7.26~会報第4号編集会議
・7.30 事務局会議(講演会準備について)
・7.31 函館東ロータリークラブ例会に、田中雪子運営委員ゲストとして卓話す。テーマ「明日の函館を考える」
・8.4 講演会(函館市公会堂於)
テーマ「函館西部の住宅とまちなみ」
足達富士夫氏 越野 武氏他北大学院生2名
事務局だより
予告
*来る10月28日(日)「上磯の歴史的風土を訪ねて』に参加しよう!詳細は後日お知らせします。
*来る11月3日4日の両日『山形の歴史的風土を訪ねて』に参加しよう!山形の文化人との交流と詩人、真壁仁先生の講演、更に山形の優れた明治の疑洋風建築巡りを予定しております。詳細は後日お知らせします。
おねがい
新年度分会費未納の方は「振替函館630」本会宛振込をお願いします。
編集後記にかえて
*会報第4号をお届け致します。今年度も題字、中島荘手氏、カット高橋順一氏、新たにレタリング、イラスト木村訓丈氏の御協力によるものです。
*今年の秋はぬけるような青空に恵まれた。こんな素敵な秋は時間をできるだけつくって散策に出かけるに限る。それも早朝と黄昏どきが味わい深い。多分郷土の美しさを再発見するに違いない。西部に限ると…函館公園→護国神社→ロープウェー→元町水源池→聖ヨハネ教会→ハリストス正教会→カトリック教会→市公会堂→旧渡島支庁庁舎→旧英国領事館→基坂→石畳…いつ歩いても周辺たた住まいはバタ臭く函館らしい美しい風情である。特にカトリック教会のポプラの樹間に部厚く横たわる石塀は道一本隔てたハリストス正教会を大きく支え引立てているよう。ふと、この街路に美しいベンチがー定の間隔を置いてあったらと思う。それは何処かのまぎらわしい広告が入ったそれではなく、ロココ調と言おうかラールヌーボー調のまっ白い、日本式なら差詰め唐草模様の鋳物で多少華奢な中にも風雪に堪えるだけの、そんなベンチが何気なく其処ここにあったら、一段と散策も楽しくなるのでは、と深まりゆく秋と共に感じている。<田中>
函館の歴史的風土を守る会会報 No.4 S54.9.15発行
発行所 函館の歴史的風土を守る会
五稜郭タワーKK内
函館市五稜郭町43番9号
印刷所 久保内印刷所
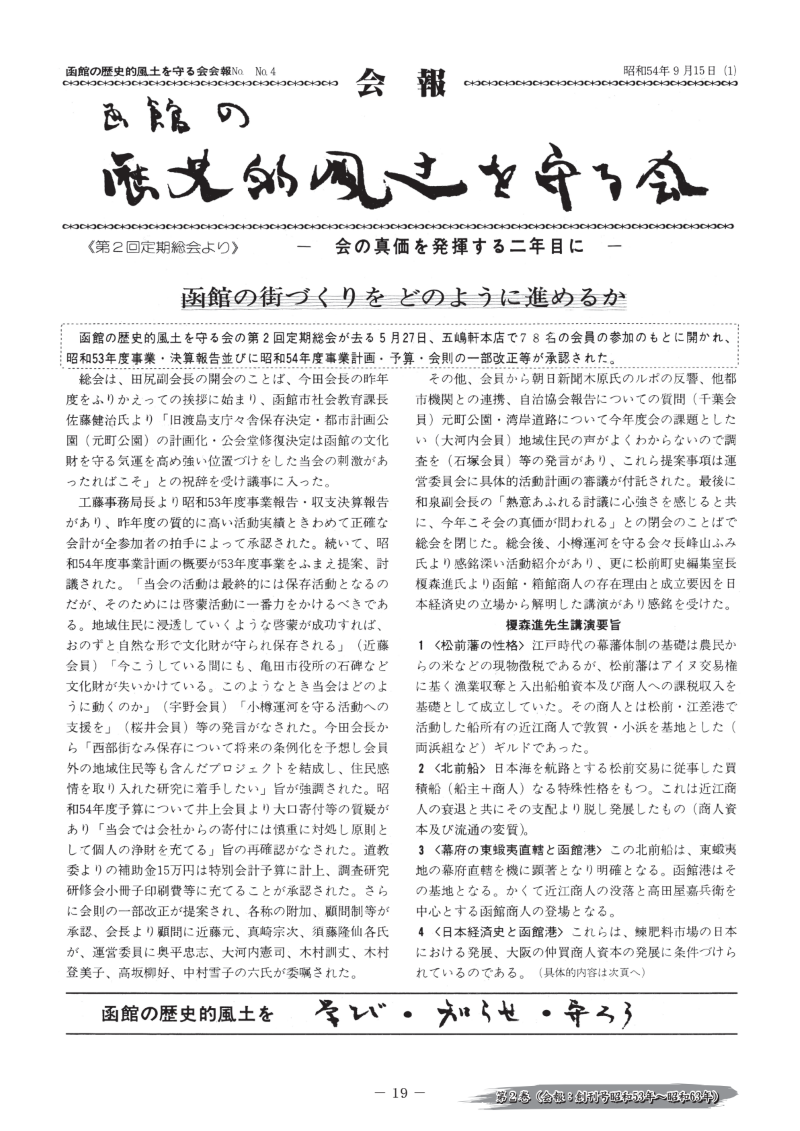


コメント